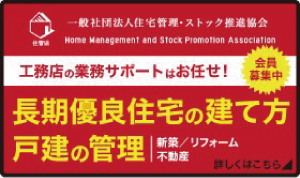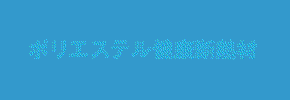新ルールに対応したリフォーム提案:床材と建築確認申請のポイント

住宅の長寿命化が求められる現代、建材の耐久性はますます重要なテーマとなっている。特に、令和7年4月から施行される建築基準法の改正により、今後新2号建築物になる建物で「大規模修繕・大規模模様替え」を行った場合には建築確認申請が必要となる方針だ。同法改正に伴い、床の修繕に関する新しいルールも設けられた。具体的には主要構造部(壁、柱、床、梁、屋根、階段)の1種以上について行う過半の修繕・模様替えを行った場合、建築確認申請が必要となる。
では、床の場合、どの工事を行えば建築確認申請の提出に該当する工事となるのだろうか。国土交通省では最下階の床は除き、改修範囲が根太にまで及ぶような改修で、改修面積が総水平投影面積に占める割合で過半となる場合は建築確認が必要としている。こうしたことから、1階の床全面張り替えなど、主要構造部に該当しない工事は建築確認申請の対象外となる見込みだ。ただし、2階の床全面改修や屋根全面改修は主要構造部の改修となり、建築確認申請が必要となる。
次に過半の判断基準はどのように行うのだろうか。これについては床、屋根などの面的な部分については、その総水平投影面積に占める割合で過半かどうかを判断する方針としている。なお、「最終的には過半を工事するつもりでありながら、短い期間で複数回に分けて施工することで建築確認提出を免れよう」という行為は、指導の対象となりうるのでやめておこう。
床材の選定方法と施工のポイント
改めて法改正は令和7年4月1日から施行され、以降工事に着手するものについて適用される。つまり、施行日以後に着工する大規模な修繕や大規模な模様替えであれば建築確認申請が必要となるが、施行日前に着工する場合は手続きが不要だ。
このため、令和7年4月1日以降も建築確認申請を必要としない範囲でリフォームを行う場合、床の仕上げ材のみの改修や既存の床に被せるカバー工法が有効となる。例えば、床の仕上げ材のみの改修等を行う場合、構造部分には手を加えないため、建築確認申請は不要となる。既存の床の仕上げ材の上に新しい仕上げ材をかぶせる改修も大規模の模様替えには該当しないので覚えておくとよいだろう。
バリアフリーリフォームの提案
上記の点を踏まえた上で、今後どのようにお施主様に向けた提案を行うべきだろうか。お年寄りのご家庭に向けたリフォームを例に考えてみよう。
工務店としては高齢者の住まい手の転倒リスクを減らすため、段差をなくしフラットな床面をカバー工法などで実現する工事を提案したいところだ。これにより、歩行補助具の使用や車椅子での移動が容易になる。また、車椅子のキャスターやフットレストによる傷を防ぐため、耐久性のある床材を選定するだけでなく、汚れが目立ちにくく、清掃が簡単な素材を選ぶことが望ましい。
そこで「今回のリフォームは、4月から施行される建築基準法の新ルールにも完全に適合しており、安心してリフォームを進められます。バリアフリー設計により、将来的な介護が必要になった場合でも安心して生活を続けることができます。具体的には玄関からリビング、廊下まで段差を解消することで、ご夫婦が安全に移動できるようになります。さらに、滑りにくい床材を使用することで、転倒リスクを大幅に減らすことができます」――。こうした説明も行えればより納得がえられるのではないだろうか。この他、バリアフリー化のためのスロープの設置工事はすべて建築確認不要なので、併せて提案してみるのもよいだろう。
住宅の長寿命化を目指す上で、耐久性の高い床材の選定は非常に重要。法改正に伴う新たなルールを理解し、適切なリフォーム計画を立てることで、安心して長く住むことができる住環境を実現できるので、制度を理解した上でルールに抵触しない施工を提案してほしい。
【日本住宅新聞2025年1月5日号より一部抜粋】
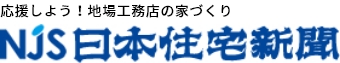

.jpg)

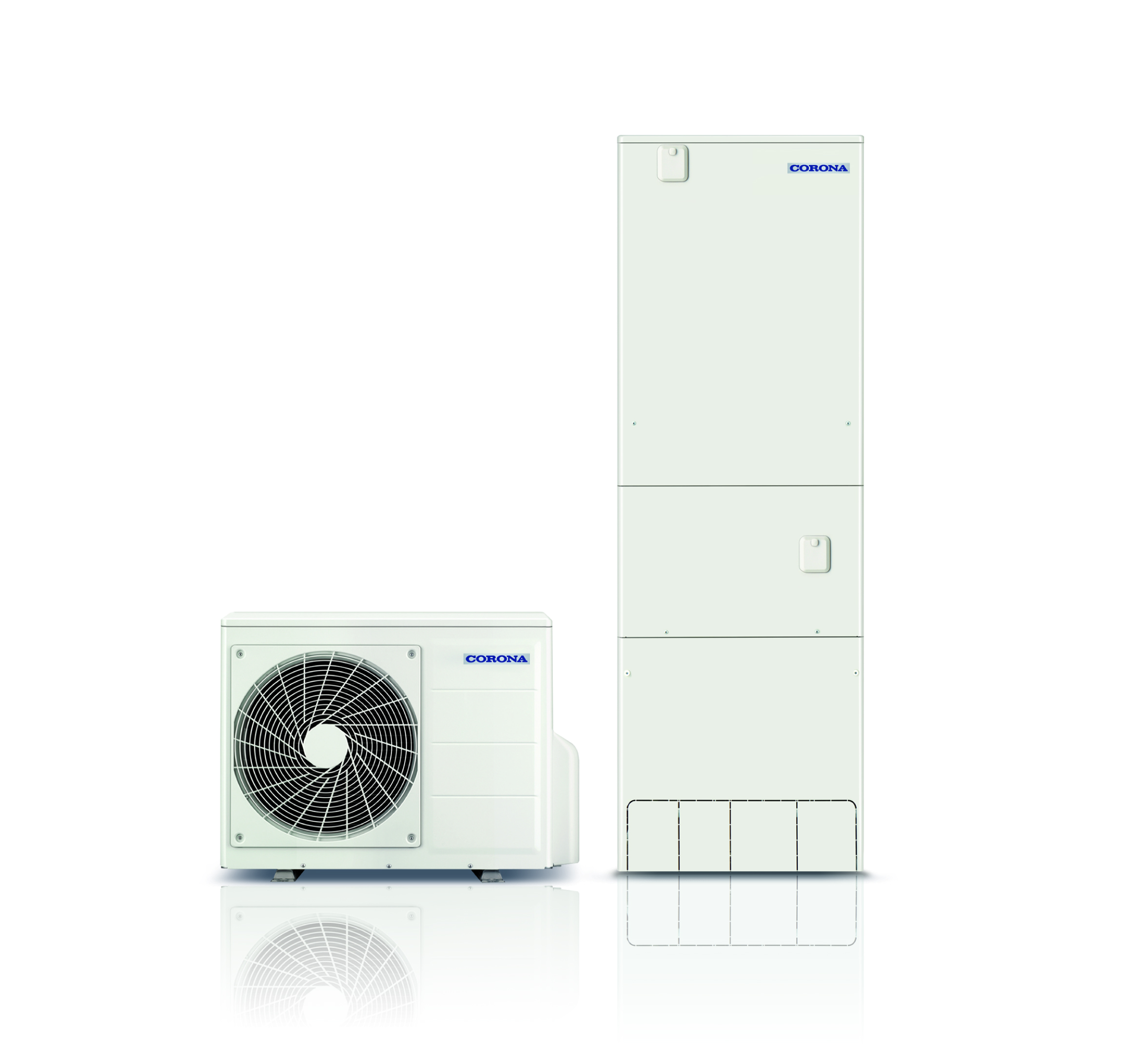
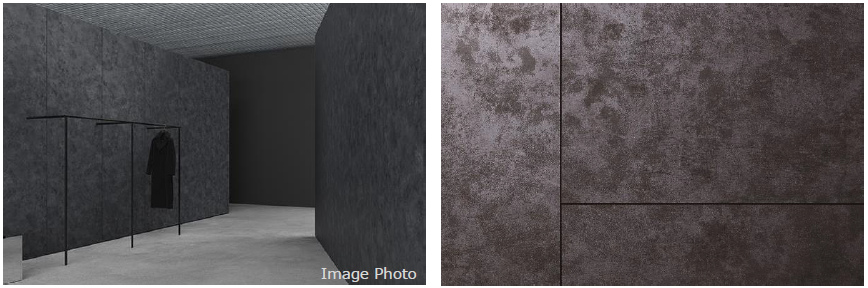



.png)