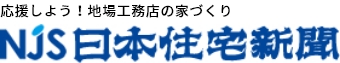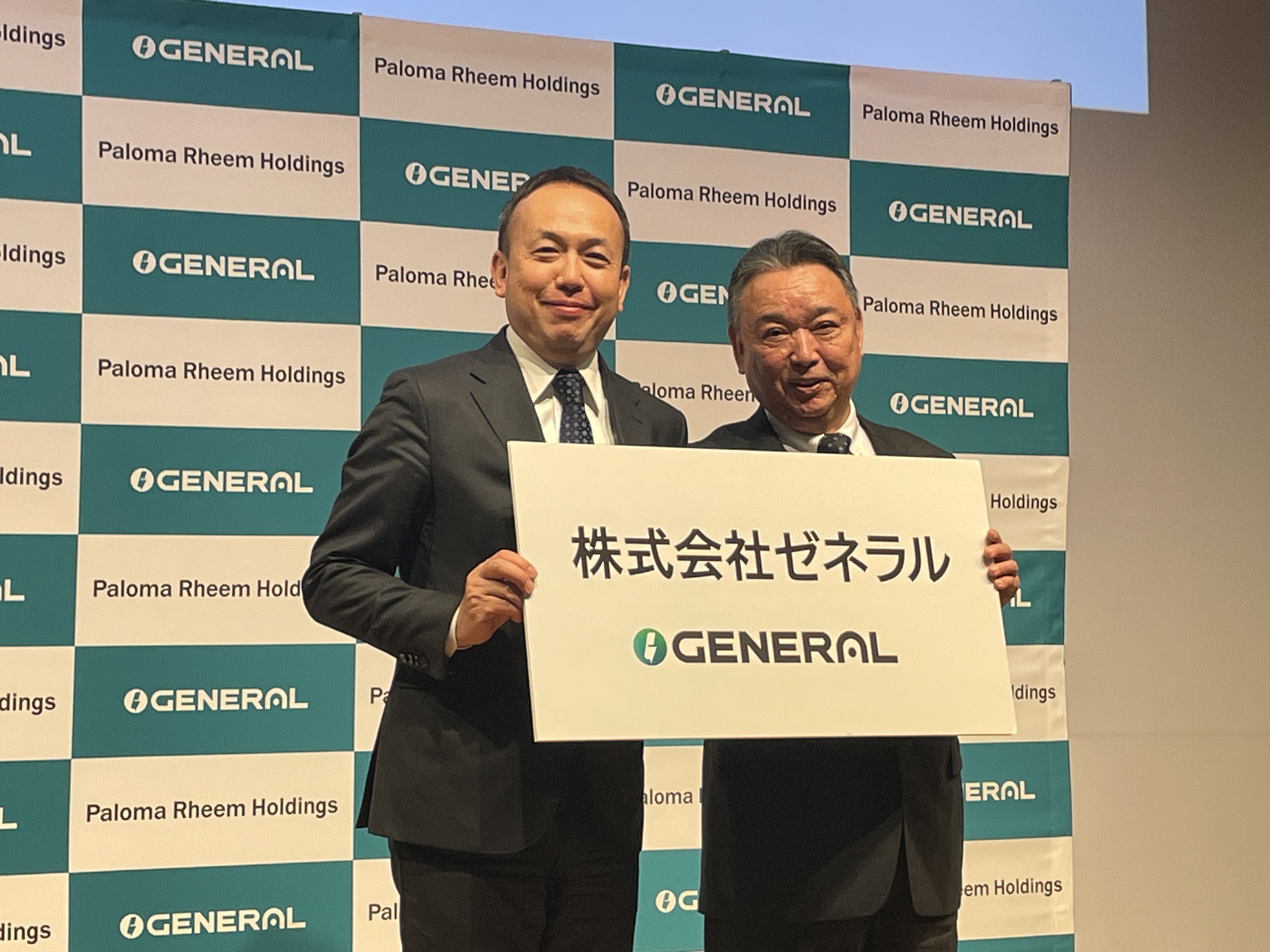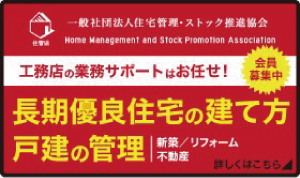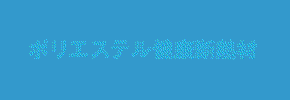断水対策の切り札 災害用井戸や湧水活用

国土交通省は3月17日、災害時に上水道が使えなくなっても地下水で生活用水がまかなえる取り組みを促進するため「災害時地下水利用ガイドライン」を策定した。国交省は19日、その説明会を開催した。対象は自治体としているが、地域防災の観点から断水時の代替水源は重要な課題であるため紹介する。
冒頭、内閣官房水循環政策本部の齋藤博之事務局長は大規模災害時における代替水源としての地下水利用は「非常に有効な手段だ」と切り出した。しかし、「実効的な取り組みが進んでいないケースも見受けられる」と現状の課題について指摘、ガイドライン策定に至った背景について説明した。
ガイドラインは主にこれから「災害用井戸」や「湧水」の活用に向けた取り組みを始めようとしている自治体を対象に、その手順などについてまとめたもの。地域の防災力を向上させる一助として役立てる。
災害用井戸とは、地震など自然災害によって断水が発生した場合に、上水道が復旧するまでの間、その代替となる生活用水として地域住民に提供する井戸のこと。民間企業や井戸の所有者と井戸水提供の協定を締結することにより、災害時の利用を予定している井戸も含まれる。
既設の井戸を災害用井戸として活用する際は「地域の共助の精神」に基づいて、井戸所有者が日常使用している井戸の水を無償で提供することを原則とする。「湧水」についても同様だ。
災害用井戸
災害用井戸の水は洗濯や風呂、トイレなど生活用水として使用する。災害時にインフラが復旧する順番は電気、水道、ガスとされるが、実際に2024年1月1日に発生した能登半島地震でも断水被害の復旧遅れが目立った。総務省が公表した石川県七尾市における1月9日時点の被害状況によると、電力はほぼ全域で復旧済みとなっていたが、断水は約2万戸で解消されていなかった。断水が解消したのは約3カ月後だった。
災害時の水
必要量は
避難生活の時間が経つほど必要な生活水量は増える。熊本市が公表する熊本市地域防災計画によると、応急給水の目標水量は発災から3日目までは1人あたり1日に3Lの飲料水が必要としている。しかし、10日目には飲料水に加えて炊事など最低限の生活を営むために給水量は20Lまで跳ね上がる。21日目にはこれらに加えて洗濯もするために100L、28日目には入浴なども行うために250Lが必要としている。
災害用井戸、湧水の水質は、飲用を目的とする場合は水質基準の設定が必要だが、ガイドラインでは生活用水を対象としているため、厳密な水質基準を求めないこととした。
しかし、こうした井戸は長期間使わないでいると目詰まりなどが発生して水質が悪化する場合がある。これを避けるために普段から使えるような環境にすることが望ましい。具体的には地域の公園に設置されている井戸の場合、自治会が公園の清掃や植樹への水やりに井戸水を使ったり、子どもが水遊びに使ったりするケースなど普段から活用される井戸のあり方が理想だ。
また、住民が水を容器などに入れて運ぶ際、無理なく運べる場所に既設の井戸がないなど新設井戸の検討が必要な地域もある。この際、ガイドラインでは「住民が無理なく手で水を運べる距離(約500m)を考慮して、災害用井戸の配置を検討することも有効」と指摘している。
【日本住宅新聞2025年4月5日号より一部抜粋】