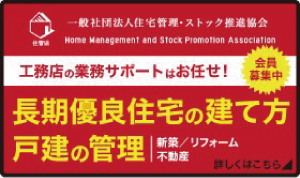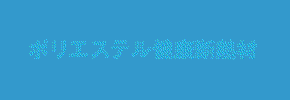仮設住宅建設の意義と工務店の役割

年初の能登半島地震で大きな被害を受けた石川県。発災から間もなく150日が経とうとしている現在も、被害の激しかった地域では倒壊した住居が未だ撤去されず、道路はひび割れ、そのまま手つかずになっているのが実情だ。こうした中、一日も早い実現を求められるのが、被災者の生活再建。中でも安全や健康、プライバシーの保護、家族や地域社会とのコミュニケーションの確立に必要不可欠なものといえば、やはり住宅といえる。
このような背景にあって、(一社)全国木造建設事業協会(全木協・大野年司理事長)は現在、石川県から応急仮設木造住宅建設の依頼を受け、輪島市、珠洲市の2市7団地で551戸の木造仮設住宅の建設を進めている。建設中の7団地のうち3月上旬に着工した団地が完成の見込みとなっていること、2階建ての応急仮設木造住宅の工事も始まったことから、5月11日に石川県における応急仮設木造住宅現地視察会を開催した。
全木協は、全建総連がJBN・全国工務店協会とともに運営する団体。大工・工務店の業務、技術、人材育成への支援を目的とした事業を展開している。これまで被災地・被災者支援にも取り組んできており、東日本大震災、熊本地震、平成30年7月豪雨(愛媛・広島・岡山)などの際、全国から職人を派遣し、木造建設型仮設住宅を建設した実績を持つ。
もちろん本来、建設工事への労働者派遣は労働者派遣法又は職業安定法違反として罰則(1年以下の懲役または100万円以下の罰金)が適用されるもの。だが、例外的に職業安定法第45条では労働組合が厚生労働大臣の許可を受けた場合、合法的に労働者供給を行うことが可能となる。
そこで全木協では仮設住宅建設の受注・施工管理等を担うJBN会員企業に、労働組合法人である全建総連が大工技能者を送り出す労働者供給事業のスキームを活用。被災地での活動を円滑に運営している。
今回の仮設木造住宅建設ではJBN会員企業の㈱エバーフィールド(熊本市)、タカノホーム㈱(富山市)の2社が受注、設計等を担い、被災地域の工務店と連携して現場管理を実施。全建総連が2社に対し組合員大工技能者を供給する形を採用している。雇用される人材は最終的に延べ1万5000人工を超える見込みという。
視察会場となったのは、輪島市の鳳至(ふげし)小学校仮設団地と町野仮設団地の2カ所。初めに訪問した鳳至小学校仮設団地はその名の通り、小学校のグラウンドに建設されている仮設団地だ。
住宅戸数107戸・29棟を予定しており、坪数6坪・9坪・12坪の3タイプが用意されている。間取りは1DKが73戸と車いすタイプが1戸、2DKが24戸と車いすタイプが1戸、2LDK(2階)が8戸。この他、集会所1カ所、駐車場は3台分となっている。
当日、エバーフィールドの久原英司社長が現地であいさつ。同団地で建てる仮設住宅はRCの基礎を使った木造仮設住宅であること、2年後には基本的に無償譲渡する予定であること、20~30年間使い続ける想定で建設していることなどを解説した。
さらに今回は初めて2階建ての木造の応急仮設住宅を手掛けている。応急仮設住宅では、面積が狭くなってしまうのが悩みの種。そこでメゾットタイプの2階建てとすることで6坪の敷地でも12坪分の延べ床面積が有効利用できると見込まれることから、このような住宅を用意したと説明した。加えて、仮設住宅には全て屋根裏収納を用意。居住空間を確保するための工夫がみられるつくりとなっている。
仮設住宅に使用する資材は全て石川県の日本木材青壮年団体連合会(木青連)を通じて入手したもの。積雪荷重の兼ね合いから梁だけは米マツを利用しているが、その他は基本的に地元の材料を中心に杉材、ヒノキ材を多く利用しており、国産材比率はおよそ90%弱に達するという。また、木材についても、加工材を直接調達するのではなく、石川県で製材加工を行うことで、地域を挙げた復興に取り組む住まい造りの仕組みを採用していると紹介した。
【日本住宅新聞5月25日号より一部抜粋】
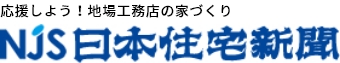


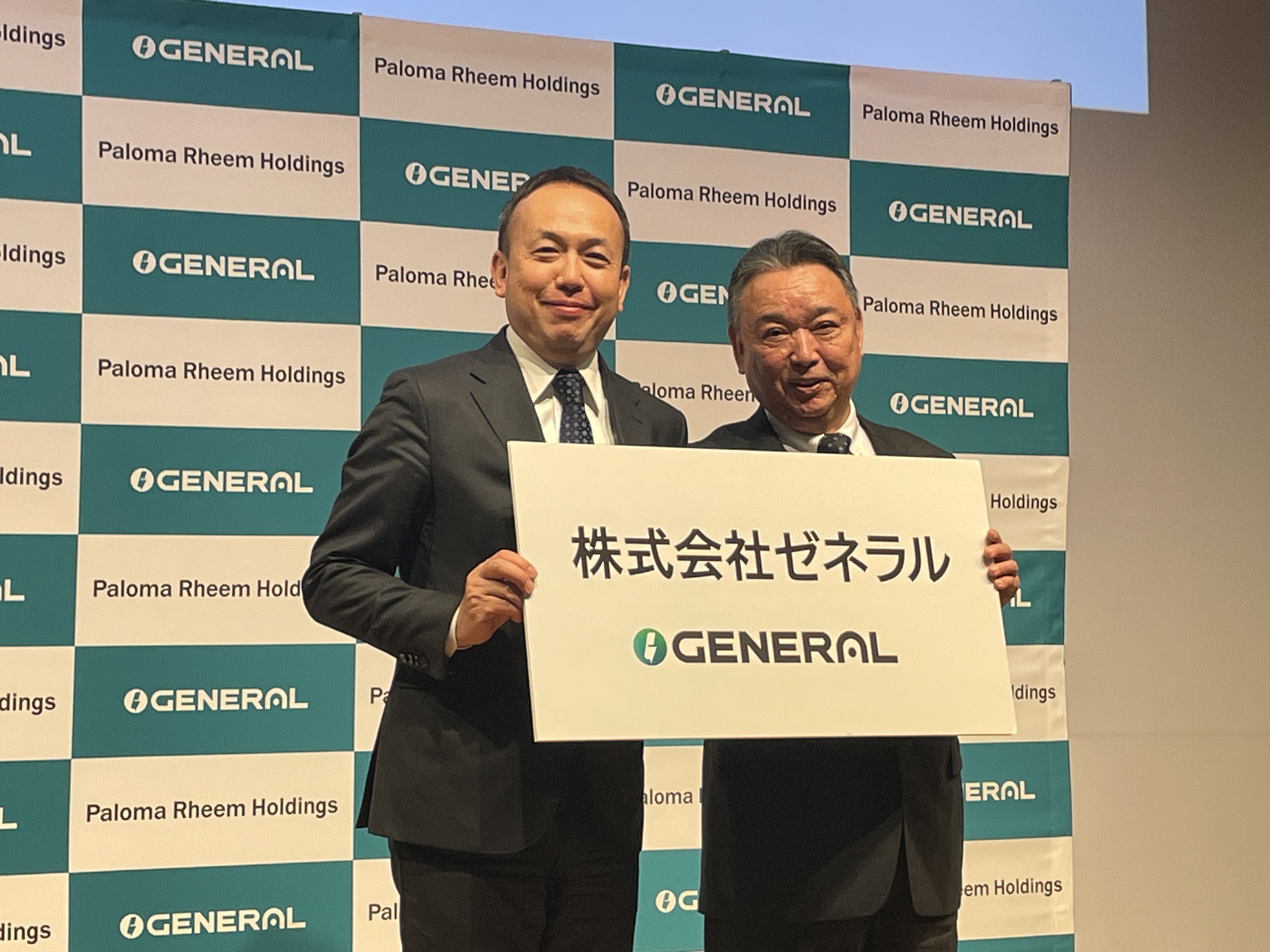






.jpg)