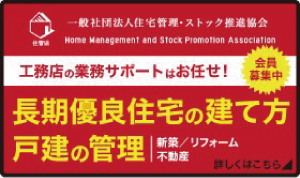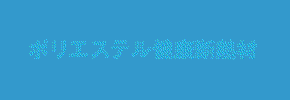改正法ついにスタート 対策は?

4月1日に施行された建築物省エネ法および建築基準法の改正。建築確認申請の際に新2号建築物では省エネ関連や構造計算関連の書類提出が求められることになることから、混乱が生じるおそれがある。こうした中、設計事務所はどのような対応を行っているのだろうか。今回、3社の設計事務所にお話を伺った。
「現状、業務の混乱や支障等は特にない」と答えてくれたのは木造建築の専門家として北海道札幌市に拠点を置く一級建築士事務所「J建築システム㈱」だ。「3月初め頃は、長期対応の構造計算を改正前に申請したいという物件がかなり多かったが、今は落ち着いた状況。4月改正後は仕様規定から構造計算に切り替えていきたいという相談企業が増えているが、まだ本格的には動いていない」とした。
東京都で戸建て住宅から大型福祉施設まで木造建築物の設計業務を手掛ける「松本設計ホールディングス㈱」は、制度施行前の3月末時点において特に駆け込み依頼などは見られなかったという。「4月以降でなければ申請機関が本請けに切り替えられないことから、多くのお客様は比較的ゆとりを持って準備されていました。ただ、これまで約一週間で交付されていた確認申請も制度変更により審査に時間を要することが予想され、着工時期を明言できない状況であることは、あらかじめお伝えしています」と話す。
また「意匠設計をメインに行っている設計事務所がコストアップのあおりを受け、困っているようだ」と話すのは奈良県で構造設計をメインに手掛けるA設計事務所。「特にこれまで壁量計算を行わず、4号建築物関連の特例に頼っていた人たちは安く外注できるところを探しているのが実態ではないか」と指摘する。
最大の懸念点は?
今回の法改正を受け、構造設計を行う各社が最も懸念している点は何か。J建築システム㈱が挙げるのは以下の3点。①申請から確認がおりるまでの日数の長期化、②不足書類などのやり取り等、工務店がうまく対応できるか、③構造計算書有りで申請する場合に、設計者が構造図一式を正しく揃えられるか――だ。
また、対応が難しい点として「いざ、構造仕様の審査を受ける際、現在の仕様で良いのか判断がつかないビルダーがかなり多い」と指摘する。その上で「今まで、図面に明記していなかった項目をどのように記載するか、検討中の会社が多い」とした。
松本設計ホールディングス㈱からも「これまでは確認申請の後に省エネや構造関連の書類を提出する流れでしたが、今後は確認申請の前に評価に関する書類を揃えておく必要があります。こうした変更点について、まだ十分にご理解いただけていないお客様も多く、丁寧に説明する場面が増えています」との声が聞かれた。
どう対策すべきか
こうした中、改めて工務店がどのように対応するべきかアドバイスを頂いた。
松本設計ホールディングス㈱は「確認済証を取得することよりも、“検査済証”が下りるかどうかに、より注意してほしい。鉄筋の配筋写真や認定書の保存、コンクリート強度試験の記録などが、突然求められることがあります。これらは従来から義務とされているものですが、対応が曖昧な工務店も少なくありません。また、建築士事務所として15年間保存が義務づけられている設計図書の中には、工事報告書も含まれる。その報告書を最終的にきちんと保管されている会社がどれくらいあるのか不安に感じます。検査時に写真の提出もなかなかされないケースも多く、義務であるにもかかわらず浸透していない現状があります」と警鐘を鳴らす。
また、A設計事務所からは「今回の法改正を受け、審査側にも混乱が生じると思う。だから焦って仕事を進めるのではなく、ここは会社を一年間休業してでも職人から監督まで全員が制度内容を理解できる体制を整えてから受注するべきではないか」という厳しい意見が寄せられた。
各種サポート活用を
今回の法改正は住宅分野において大きな転換点となるもの。一方で各社が指摘するように制度初期には工務店側、審査側共に様々な混乱が起こることが考えうる。改めて各工務店は十分に情報収集を行った上で最新の制度に対処できるよう自社をアップロードさせてほしい。
中には構造計算の内製化を目指す企業や今後構造計算を覚えたいという方もいらっしゃるだろう。こうした中、構造設計事務所をはじめ、各種機関によるサポートを受けることは持続可能かつスムーズな工務店経営を行う上で有効な対処法だ。
実際、J建築システムからは「弊社では4号特例の見直しを正しく理解し、木造住宅の構造計算の基礎をしっかり学べる『jjjスクール』を開校中です。対面による少人数制研修、入力エラーから計算エラー回避までを習得できますのでぜひ、ご利用ください」といった案内も聞かれた。
自社のみでの解決にこだわらず、必要に応じて各種機関・団体にご協力頂くことも視野に入れ、この難局に立ち向かっていってほしい。
【日本住宅新聞2025年4月5日号より一部抜粋】
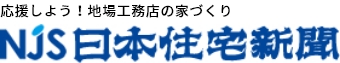





.jpg)