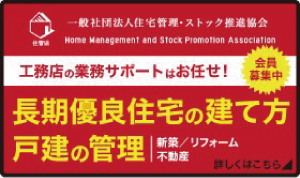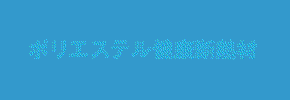完工棟数は減少の中 労働災害は増加
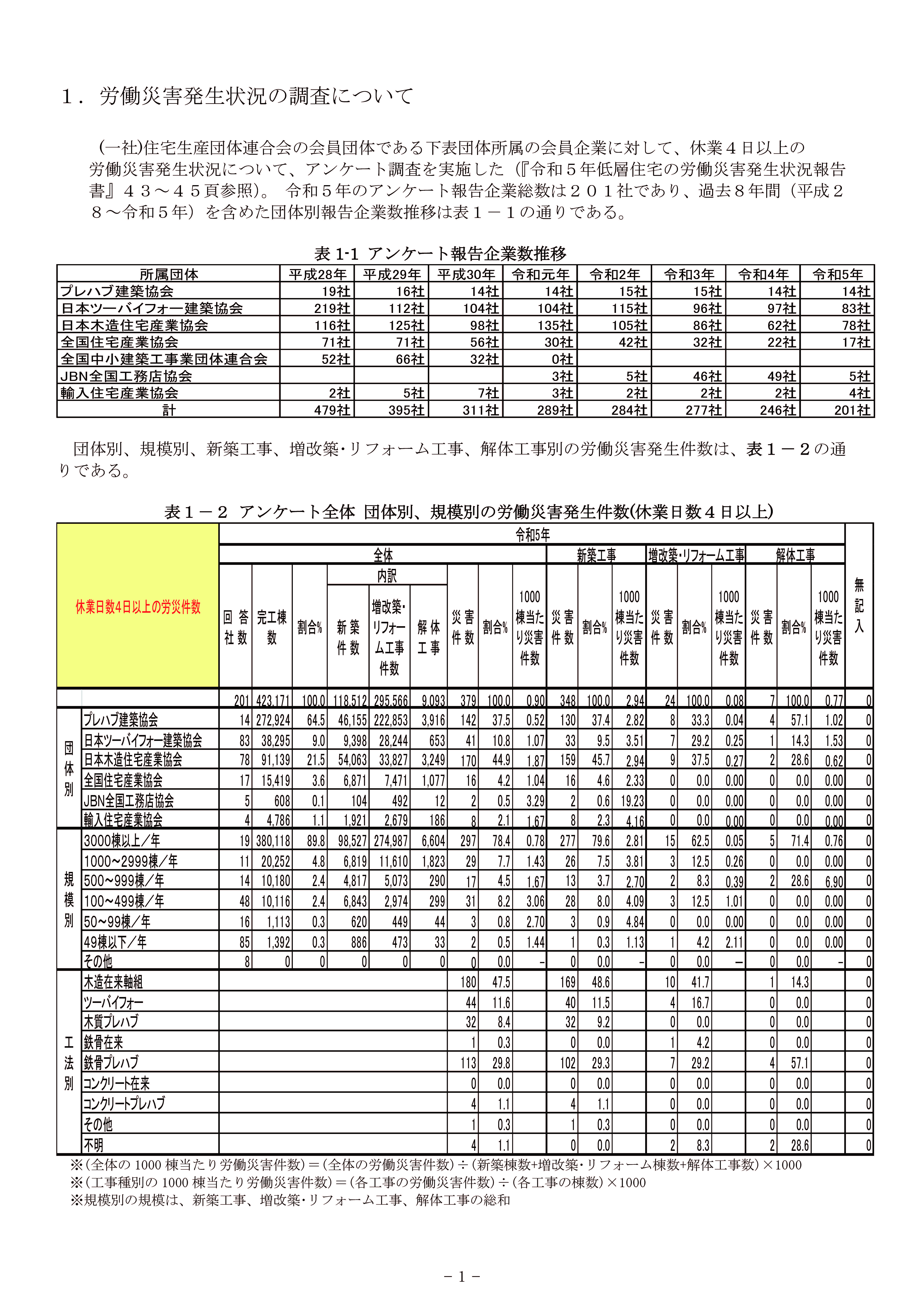
(一社)住宅生産団体連合会は、「令和5年低層住宅の労働災害発生状況報告書」を7月19日に公表した。
令和5年(1~12月)の調査企業数は201社(前年より45社減少)で、完工棟数は「新築」が11万8512棟(前年比120%)、「増改築・リフォーム」が29万5566棟(前年比89%)、「解体」が9093棟(前年比92%)。そして、労働災害件数は379件(前年より53件増加)だった。
労働災害発生件数(絶対数)をみると、完工棟数の合計が1万6468棟減少(前年比96%)している中、全体として53件増加(前年比116%)となった。内訳は新築工事で54件増加(前年比118%)、増改築・リフォーム工事で2件減少(前年比92%)、解体工事で1件増加(前年比117%)となり、新築工事が全体を増加させる形だった。
令和5年の1000棟当たりの規模別労働災害発生件数は、全体としては増加(令和3年が0・93、令和4年が0・74、令和5年が0・90)となっている。住団連は「全体増加の要因としては『3000棟以上』のレンジで増加したことが全体に大きく影響している」とした。各レンジにおいては『49棟以下』、『1000~2999棟』は減少し、『50~99棟』、『100~499棟』、『500~999棟』、『3000棟以上』は増加となった。
内部造作工事
昨対比約2倍の増加
令和5年においては、基礎、足場、建方工事の災害発生比率が若干減少したが、内部造作工事で昨対比約2倍の顕著な増加に転じ、外部造作、外装でも増加している。そして、建方と内部造作工事を併せると全体の約5割の事故発生となっており、重点的かつ恒久的な改善が急務となっている。
住団連は「❶建方工事においては墜落制止用器具(フルハーネス)を着用し、フックを腰より高い位置に掛けて作業するなど基本動作の徹底と足場設置基準遵守などの作業環境の整備が重要となってくる。❷内部造作は脚立が使われることが多いが、手軽に扱えるということと高所作業ではないという油断から不安全行動を誘発しやすい環境にあるため、天板上での作業禁止はもちろん脚立の正しい使い方を遵守させるとともに脚立に替えて足場台の普及促進が必要である。❸電動工具については定期点検の履行はもちろん、日々の作業開始前・作業終了後の点検並びに作業手順の周知・理解を徹底させることが肝要である」とした。
「大工」・「その他」
約8割占める
令和5年の職種分類別労働災害発生状況は、「大工」の労働災害が全職種の約4割を占め、現場での作業時間が最も長い「大工」が例年と同じく全職種中最も高い発生割合となっている。また、前年11ポイント減少した「大工」が、今年また増加している。住団連は「これは大工においては職人の高齢化が進んでいる職種であり、労働災害発生は高齢化による身体の衰えの影響もあると思われる。今後もその傾向は注視していくべきである」とした。
「その他」の職種では、例年同様に全体の3割を超える災害が発生している。「その他」の職種の中では、作業環境が不安定な「解体」作業での労働災害や、一現場に長期滞在しての作業を行うことが少ない多くの現場を巡回する職種は、現場毎の作業環境に不慣れゆえの労働災害が発生している。
一方、「現場監督」・「納材」といった職種の災害発生状況は減少が見られた。住団連は「これは現場での資材搬入時の安全通路や、配置計画、現場の整理・整頓、スピーディな残材処理等、現場での安全管理が徹底されてきた成果であり、現場管理者においては引続き、安全管理を徹底していく必要がある」とした。
また、令和5年の原因・型別労働災害発生状況は、近年減少傾向ではあるものの依然として「墜転落」(40・6%)が最も多く発生。続いて「工具(切れ・こすれ)」(20・1%)、「転倒」(14・8%)の順となっている。
年齢層別労働災害発生状況では、令和5年は令和4年に比べ50歳代から60歳以上で増加し、20歳未満、20歳代の年代層
でも若干増加が見られたが、40歳以下全体の年代層では減少の傾向が見られた。令和5年全体で見ると60歳以上の割合が26・4%と大きな割合を占め、前年より0・9%増加している。50歳代も前年より1%の増加がみられ高齢者の割合が増加している。住団連は「今後も低層住宅工事に携わる高年齢化と、若い外国人労働者の増加が予想されるため、高年齢層を含めた低年齢層の災害発生比率の増加が懸念される」とした。
【日本住宅新聞8月5・15日合併号より一部抜粋】
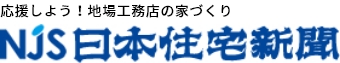


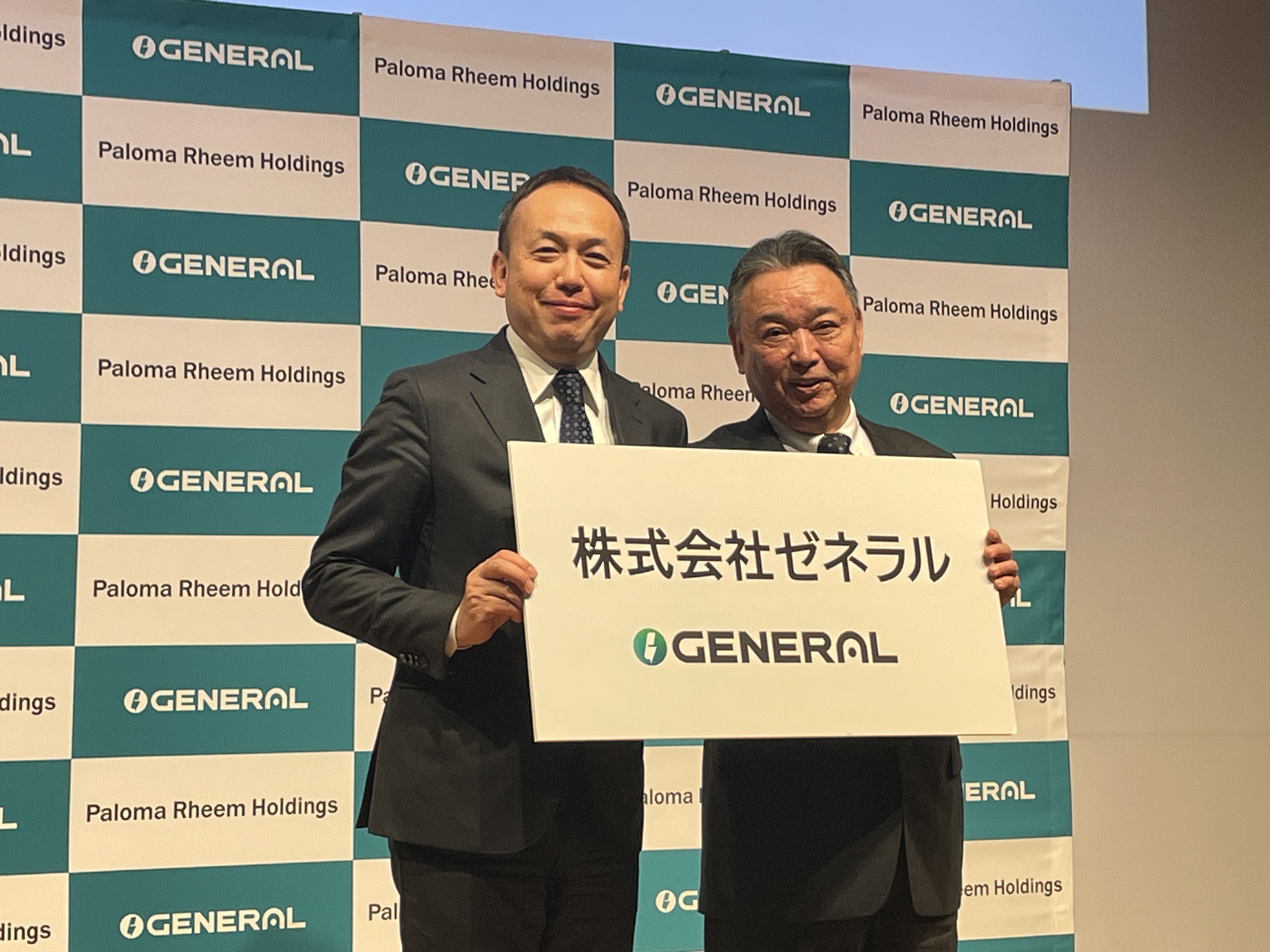






.jpg)