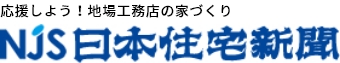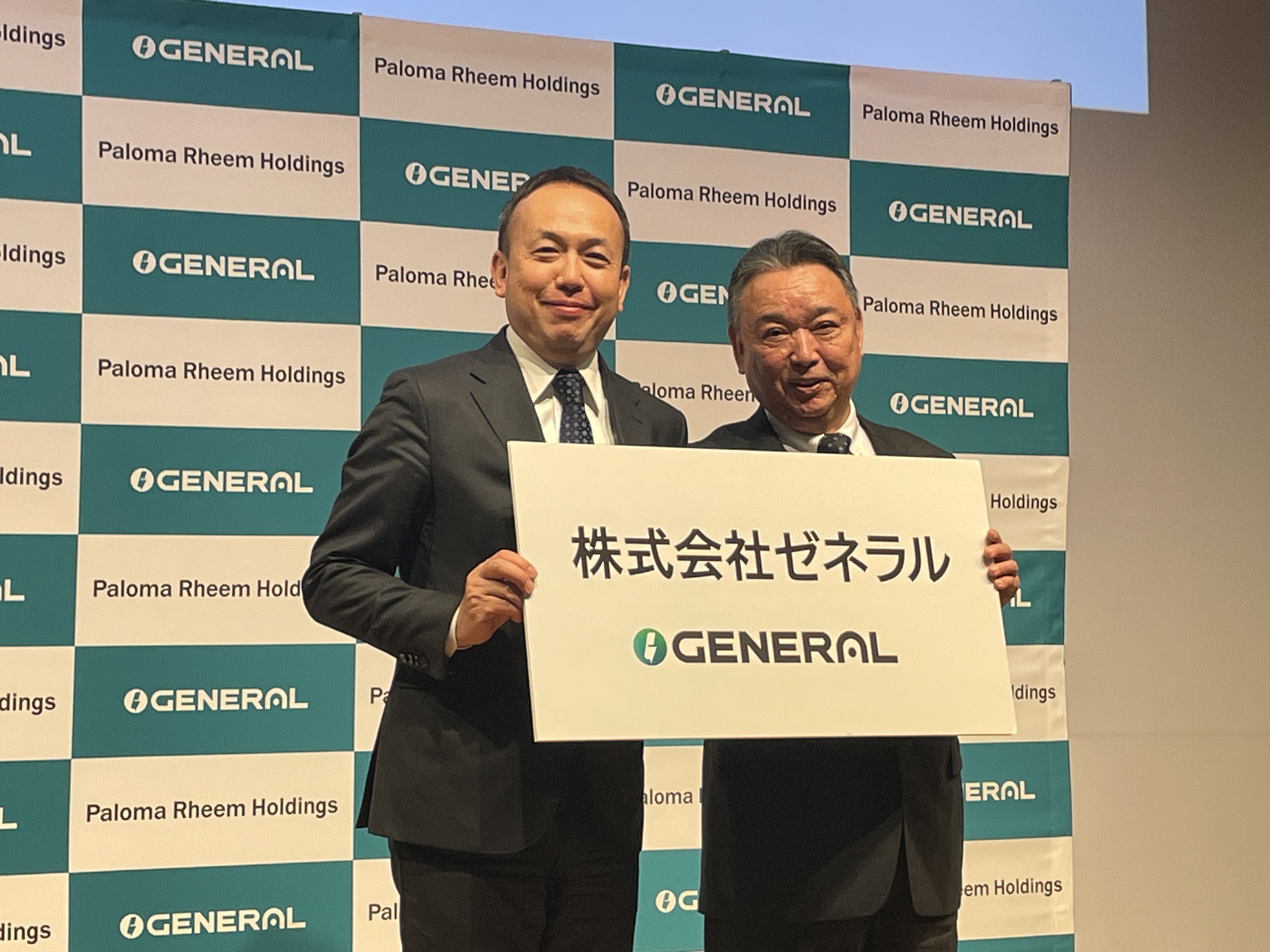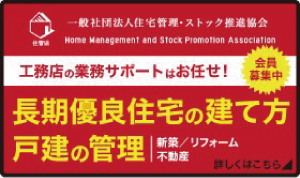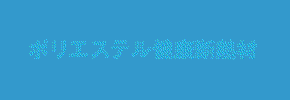厚労省イクメンプロジェクト 外装工事会社 ㈱スエヒロ工業(静岡県沼津市) 施工管理の男性従業員が育休取得 社内環境整備の副産物は主体性

厚生労働省は男性の育休取得を推進する事業「イクメンプロジェクト」を実施している。その一環として厚労省は2月10日、育児しやすい職場の作り方をテーマにした企業向けシンポジウムを開催した。この中で建物の外装全般を請け負う専門工事会社の㈱スエヒロ工業(静岡県沼津市)が登壇。建設業界における男性育休の取り組みについて紹介した。
今回発表したのはスエヒロ工業で男性育休の取得促進に向けた取り組みを行ったダイバーシティ推進部の大野友美部長と企画推進室の石山千華室長だ。大野部長は育休を取得する本人のケアや後述する「業務の棚卸し」などを進め、石山室長は社内で育休を推進する上での調整業務を主に担当した。両名は「子育ての真っ最中」(石山室長)であり、その経験も今回の取り組みに活かした。
育休を取得したのは当時入社7年目の男性社員Aさん。施工管理を担当しているため、複数の現場を見回りながら帰社して事務作業を進める働き方をしていた。石山室長は「勤務時間の8~17時に様々な場所に移動しているイメージ」だと本人の働き方について説明した。
Aさんは子どもが生まれるタイミングで11日間の育休が取得できた。その実現にあたって取り組んだことが現状把握だった。社内調整を担当した大野部長は「とにかく時間がない、何をしなければならないのか(分からない)」ところからスタートしたと話し、こうした状況からいち早く脱却するためにも現状の整理が必要だったと振り返る。
そこで業務内容の整理となる「業務の棚卸し」を進めると「本人の業務を他の担当者がすべてフォローする必要がないことに気づいた」(大野部長、以下同)という。また、Aさんのスケジュールの中で業務内容を育休に入る前と後に振り分け、他の社員に負担がかからないように考慮した。
育休を取得する前、Aさんは自分の業務量が把握できておらず、他の社員においても「なんとなく会社にいる」、「とりあえず出社する」といった傾向があったと指摘する。
こうした傾向が育休取得の環境整備の一環で変わった。従業員が意識して自分の業務量の全体量を把握し、優先順位をつけてタスクをこなすようになったのだ。ワークライフバランスも意識できるようになり、「自信をもって業務に取り組めるようになった」という。
会社の体制にも変化があった。育休取得前には業務が個人に紐づいており、個人が複数の現場を管理する状況だった。しかし現状は現場の状況をチームで共有する時間が設けられるようになり、急な家族のケアで休まざるを得ない場合でも「安心して他の社員にお願いできるようになった」という。
最後に大野部長は「今回の育休は社内体制の準備が不十分で準備期間が短かったため、完璧にできたとはいえない」と話したが、一方で「完璧に制度を整えてからスタートしようとしたら、実現しなかったともいえる」と振り返った。
一般的に現場仕事が主体となる建設・建築業界での働き方改革は難しいとされる。しかし、同社のような好例はある。従業員とコミュニケーションを図りつつ、できることを着実に進めていく重要さが伺える事例といえるだろう。
【日本住宅新聞2025年2月25日号より一部抜粋】