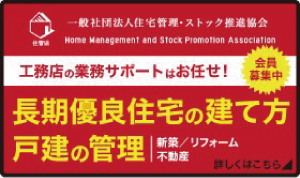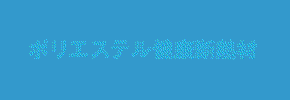改正法施行に向け準備は万端?
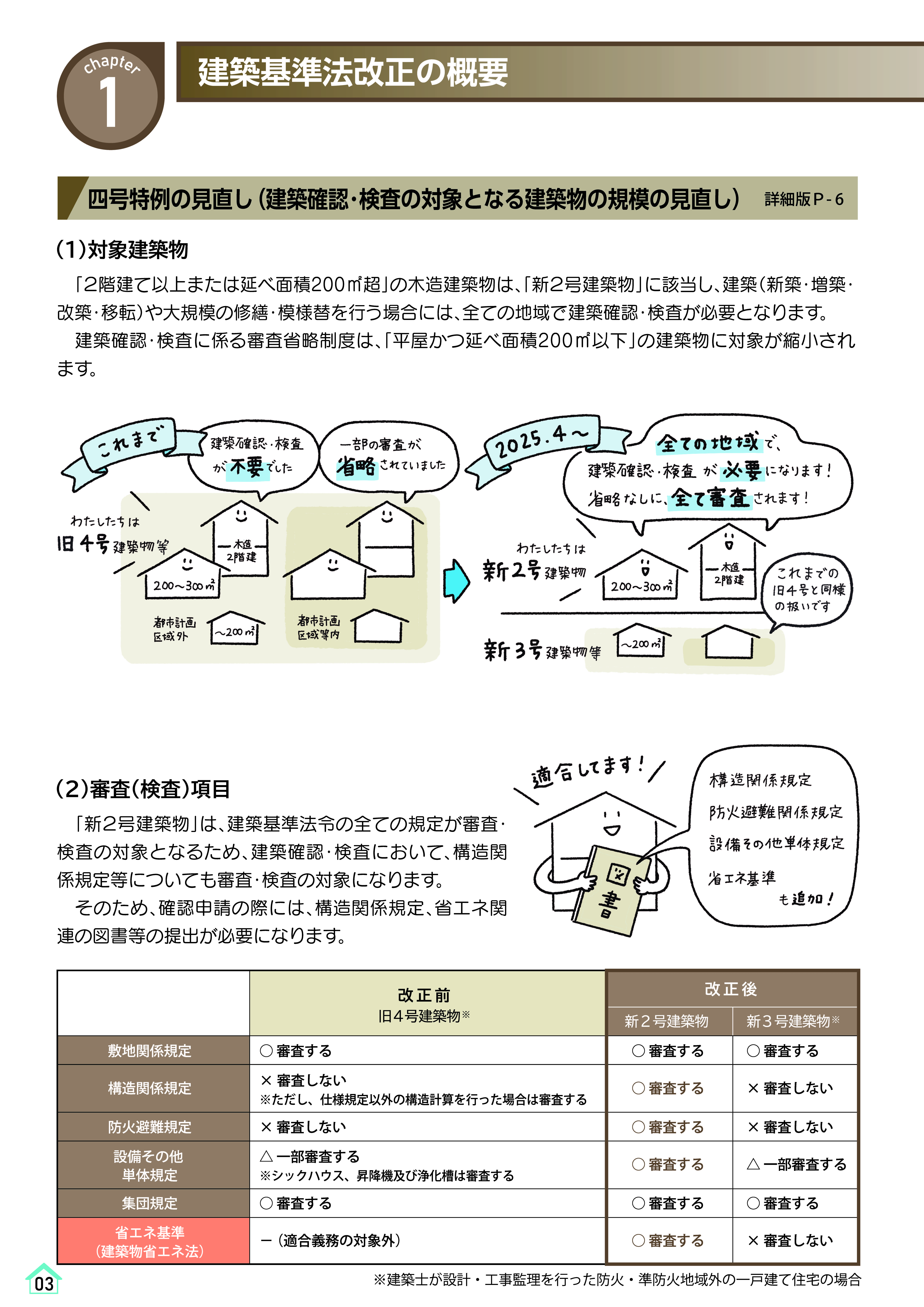
いよいよ半月後に迫った建築基準法と建築物省エネ法の改正。今回の法改正の趣旨は建築物の省エネ化とそれに付随する建物の安全性向上などを理由としたものといえる。
これまで弊紙では幾度にもわたって制度改正の内容を紹介してきたが、同改正は大変重要なテーマ。繰り返しとなって恐縮だが、改めて4月の法施行を直前に控えた今、確認の意味も含め、住宅分野においてどのような変更点があるのか、主だったものだけだが簡単に紹介させて頂く。
基準法のポイント
建築基準法の改正については㋑4号建築物の縮小、㋺確認申請手続きの変更、㋩壁量や柱の小径の基準見直し――などを押さえておきたい。簡単に触れておくと、㋑では「木造2階建て、および延べ面積200㎡超の木造平屋建て」は新2号建築物、「平屋かつ延べ床面積200㎡以下の住宅」は新3号建築物に分類される。
その上で㋺では現行の4号建築物に与えられていた審査省略制度の特例が新3号建築物のみに縮小。新2号建築物は今後、都市計画区域外であっても構造関係規定や省エネ関連の図書など、建築基準法例のすべての規定が審査・検査の対象となる。
そのため建築確認の際にはこれらの図書の提出が必要だ。完了検査においても全ての建築基準関係規定への適合性を検査することになる他、検査済み証の交付を受けた後でなければ建物は使用できない。
新2号建築において「大規模な修繕・模様替え」と呼ばれるリフォームを行う場合も建築申請手続きが必要となる。具体的には主要構造部(壁、柱、床、はり、屋根又は階段)の一種以上を、過半(1/2超)にわたり修繕・模様替えを行う物件がこれに該当する見込みだ。
木造建築物の実況に応じて算定
また、現行の壁量基準及び柱の小径の基準では、軽い屋根、重い屋根などの区分に応じて、必要壁量及び柱の小径を算定することとなっている一方、木造建築物の使用は近年多様化しているのが実情だ。そのため今後、㋩にあるように 屋根の重量の区分のみでなく、木造建築物の仕様の実況に応じて必要壁量及び柱の小径を算定できるように見直す。
なお、これについては4月1日から来年3月31日までに工事に着手するものに限り、 経過措置として改正前の壁量基準等によることができることとしている。
省エネ基準適合義務化はじまる
4月1日の改正建築物省エネ法の施行により、原則同日以降工事に着手したすべての住宅の新築及び増改築に対して省エネ基準適合義務化が求められる。省エネ基準とは、建築物が備えるべき省エネ性能の確保のために必要な建築物の構造及び設備に関する 基準であり、一次エネルギー消費量基準と外皮基準からなるものだ。このうち、増改築については4月以降、工事を行った部分のみが省エネ基準に適合すれば良いという制度に変更される。
先ほども㋺の部分で触れた通り、同基準への適合性審査は建築確認手続きの中で行われる方針だ。3月までに建築確認申請を行い、確認済証の交付を受けていても、着工が4月以降となれば基準適合義務の対象となるので注意しよう。
なお、3号建築物については「特定建築行為」から除外されているため、省エネ基準適合義務の対象ではあるが、省エネ適判は不要だ。また、建築物の省エネ性能が基準に適合するかを簡便に判定できる仕様基準を用いた場合も適合判定は省略できるので適宜活用してほしい。
新制度がスタートする令和7年4月前後には建築確認を巡り、若干の混乱が生じる可能性もある。お客様のご意向次第ではあるが、こうしたことも見越し、あえてこの時期には現行の一部図書省略が継続される「新3号」となる平屋の物件を手掛けたり、省エネ計算は仕様基準を利用したりすることで、しばらく様子を見てみるのも一つの手かもしれない。
いずれにせよ、提出図書に不備があれば、また様々なやり取りが生じることで必然的に時間をロスしてしまう。これにより工期が遅れてしまえば、最終的にお施主様にお引き渡しする時期もずれてくる。
そうなると、また新たなリスクの発生に繋がってくるので、くれぐれも事前の準備はしっかりしておくよう、おすすめしたい。
今一度確認を
改めて今回、国を始めとする様々な団体が法改正について解説する説明資料や動画を公開している。また、各地に省エネ基準にサポートセンターも設けられているので、これらも併せて参考にしてほしい。最後に弊紙編集部で改正法の理解に向けて有益なサイトをいくつかピックアップする。これらを参考に、4月の改正法施行に向け、万全の準備を整えて頂ければ幸甚だ。
【日本住宅新聞2025年3月15日号より一部抜粋】
画像:改正建築基準法2階建ての木造一戸建て住宅(軸組み工法)等の確認申請・審査マニュアルダイジェスト版より転載
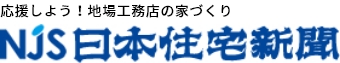


.jpg)

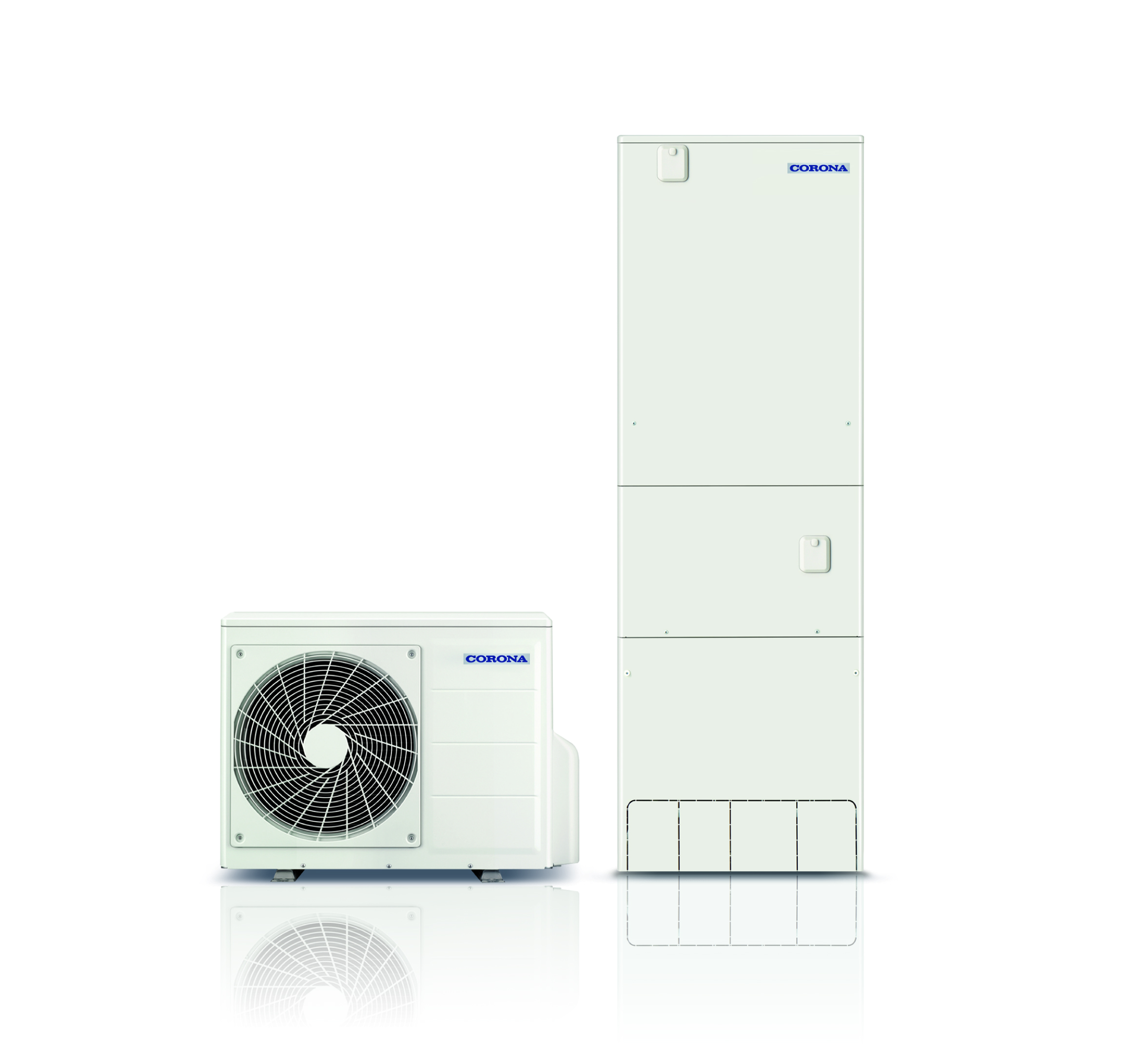
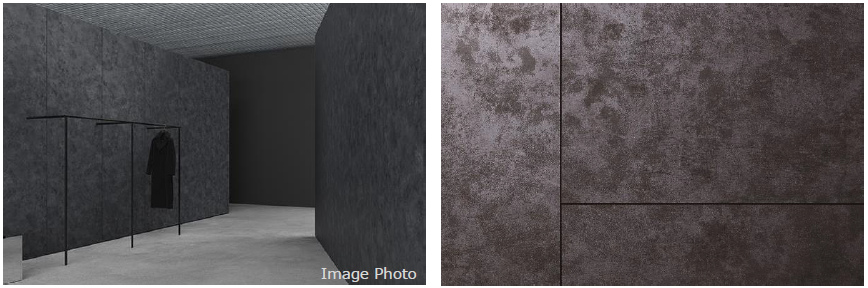



.png)