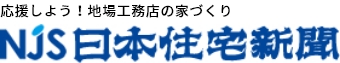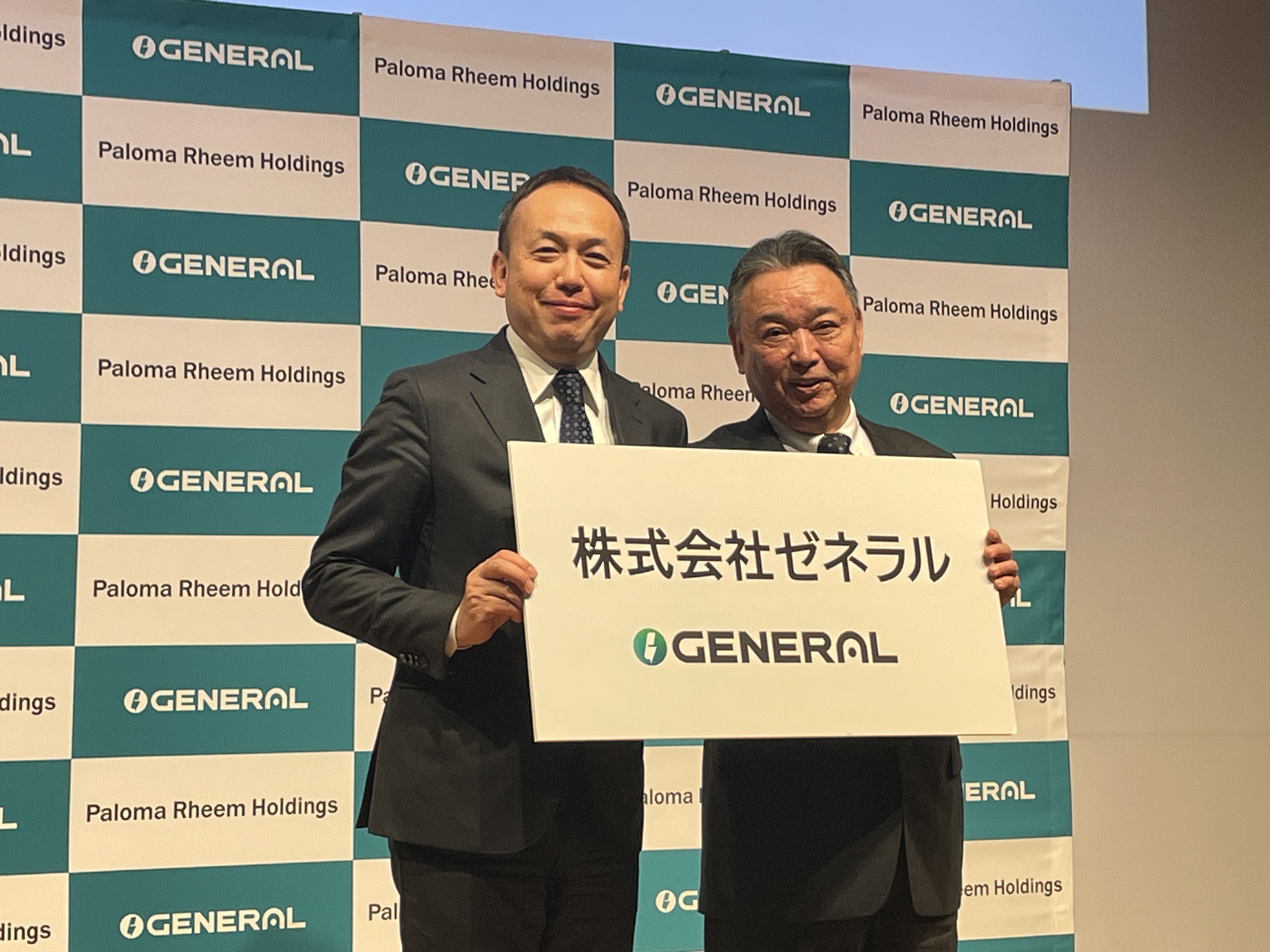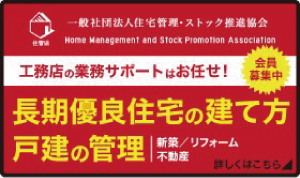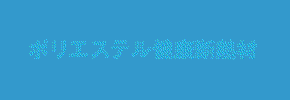50周年記念特集号(第一弾) 東京ボード工業㈱ 井上弘之社長 資源活用・環境負荷低減・経済性をセットに 環境対応はLCAの観点重要

――50周年インタビューにご対応いただきありがとうございます。早速ですが、井上社長からみてこれまでの住宅業界で最も大きかったと感じておられる変化はいつ起こりましたか。
井上社長:50周年おめでとうございます。我々は廃木材を回収し、パーティクルボードとして蘇らせる事業を行っていますが、私がこの世界に入って最も大きかったと感じている変化は平成9(1997)年の廃棄物処理法改正でした。不法投棄に関する罰則はそれまで、平成3(1991)年改正(平成4年・1992年施行)の法律が適用されていました。その内容は、不法投棄をした場合、6カ月以下の懲役、または50万円以下の罰金を適用するというものだったのです。しかし、平成9年の改正(同年施行)によって罰則が引き上げられました。具体的には3年以下の懲役、1000万円以下の罰金または法人については1億円以下の罰金を適用することとされていたのです。ちなみに、現在は平成22(2010)年の法改正(平成23年・2011年施行)によって法人の罰金は1億円から3億円に引き上げられています。さて、平成9年当時の改正によって弊社には廃木材を積載したトラックが長蛇の列をなして押し寄せるようになりました。近隣の事業者様にはご迷惑をおかけしましたが、今はこうした状況にならないよう解消しています。当時はまだ廃木材を処理するための工場のキャパシティが今ほど大きくはなかったのです。廃木材をリサイクルする需要が増加したことだけではありません。平成9年の改正は原料を確保できるようになった点としても大きな変化でした。というのも、我々の提供するパーティクルボードはマテリアルリサイクルという考え方に基づいた製品です。ただ製品を提供するだけではなく、使われなくなった廃木材を回収し、パーティクルボードに再生し、再びお客様の住宅に使われる。この循環が重要です。今でいうサーキュラーエコノミーです。樹木は長い年月を経て大気中の二酸化炭素を吸収し、固定化します。もし木材を燃やせば固定化された二酸化炭素は再び大気に放出されてしまうのです。しかし、廃木材をチップにしてパーティクルボードに加工すれば、二酸化炭素を大気放出せずに固定化したまま新たな製品として再び蘇らせることができるのです。また、直近の5~10年でお客様における環境意識が大きく変わったことも変化としては挙げられます。今は平成27(2015)年9月の国連サミットで採択されたSDGsや、菅元総理による令和2(2020)年の脱炭素宣言などによって環境対応には注目が集まっていますが、我々はそれ以前から、マテリアルリサイクルに対する取り組みを続けてきました。しかし、当時はなかなかこの考え方を理解していただくのが難しい方も一定数いらっしゃいました。
――リサイクルの重要性を理解していただくのが難しかったとのことですが、これについて具体的にお聞かせいただけますか。
井上社長:例えば、我々は平成16(2004)年に国際規格に則った枠組み「EPD認証」を取得しています。これはスウェーデンで開発された認証プログラムで製品の持続可能性や安全性を検証するものです。簡単に説明すると、製品を作る際にどれだけの環境負荷がかかったのかを提示する認証となります。つまり、認証が取得された製品であれば持続可能な基準を満たしているとみることができるのです。ヨーロッパで販路を開拓しようとしたわけではありません。当時はライフサイクルアセスメント(LCA)の評価も包括した第三者検証の仕組みは選択肢として少なかったのです(LCAについては後述)。さて、世界でも先駆的な存在だったEPD認証を取得した当時は大手新聞のトップ面に取り上げていただくなど、業界からも反響をいただきました。一方で、その中身をきちんと理解されている方は少なかったと感じております。製品板面にEPD認証のスタンプが印刷されている点についてクレームをいただいたことすらありました。しかし、最近では環境意識の高まりによってEPD認証がどういったものかを理解されている方も増えてきたと感じております。実際にヨーロッパではEPD認証が取得されている建材しか採用しなくなっているといった傾向も出てきているほどです。
――環境対応のための認証などが世間に浸透していない当初から積極的に取り組まれていた中では不安などもあったと思いますが、いかがでしょうか。
井上社長:様々なご指摘をされる方もいらっしゃいましたが、私はそれよりも大事なことがあると感じていました。むしろ、二酸化炭素排出量などを計算した上での環境対応を考えていく世の中にならなければならないと考えていたのです。当時は、経済活動を優先するあまり、環境対応はないがしろにされていました。しかし、環境対応を優先しなければ地球にはいずれ住めなくなってしまいます。環境対応の次に経済性を考えるべきなのですが、現実はその関係が逆転しているように思えます。例えば、環境対応製品には「環境にやさしい」という表現が散見されますが、この謳い文句には疑問が残ります。我々が経済活動を行う限り、環境には何かしらの負荷がかかるのです。「環境負荷が軽減される」ならば理解はできます。
――環境負荷について真摯に向き合わなければならないことが分かります。
井上社長:そのためには先述のLCAの考え方が欠かせません。これは、ある製品にかかる環境負荷を資源採取、原料生産、製品生産、流通、消費、廃棄、リサイクルの各段階を通じて評価する指標のことです。弊社の事業でいえば、廃木材の回収を行う際の物流トラックや、パーティクルボードを製造するための工場から二酸化炭素は排出されます。弊社の事業活動で排出された二酸化炭素の量がパーティクルボードに固定化されている二酸化炭素量を上回ってしまってはいけません。枯渇性資源の有効利用と環境負荷の低減はセットでなければならないのです。我々がティー・ビー・ロジスティックス㈱など運送会社をグループ会社としているのにはこうした二酸化炭素排出量を把握し、軽減していくためでもあります。重要なのはどれだけ最短距離でマテリアルリサイクルが行えるかということなのです。弊社ではこうした運搬効率の向上について「循環物流」の仕組みをとっています。これは納品と原料調達を同時に行う運搬方法です。今でいう動静脈連携です。例えば弊社の工場からパーティクルボードをトラックに積載、運搬し納品。納品先の現場からは廃木材を回収して再び工場に戻るといった方法です。これは一般貨物運送と産業廃棄物運搬・処理の許可を取得していなければできません。弊社製品の原料調達は、関東最大級の木質廃棄物処分場を拠点とし、他社に比べて優位な処理能力を持っていると自負しています。実際に「壁武者」の原料調達はその9割が関東圏からです。そういった意味では、拠点の周りに原料となる廃木材を確保できる環境はあるため、我々が供給する資材の原料は確保できる体制となっています。
【日本住宅新聞6月15日号より一部抜粋】