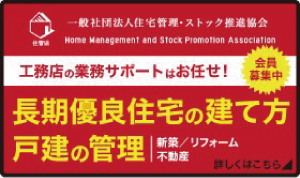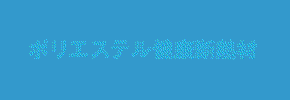大規模地震時の電気火災対策として 感震ブレーカー等の普及を推進する
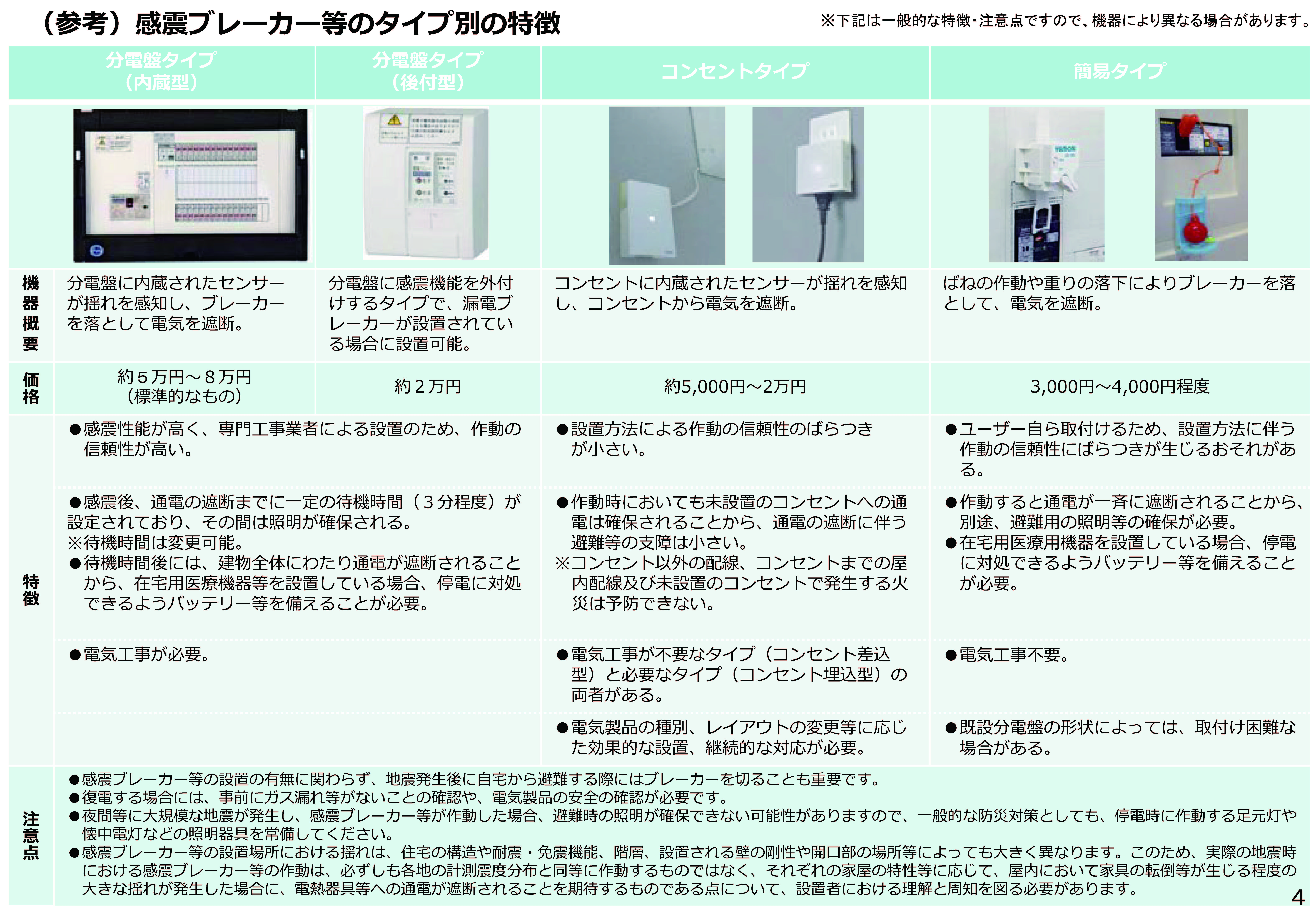
過去の大規模地震において、電気を原因とした火災が多く発生している。平成7年の阪神淡路大震災においては139件の地震火災のうち、電気火災が85件(約6割)、平成23年の東日本大震災においては108件の地震火災のうち、電気火災が58件(約5割強)発生した。令和6年能登半島地震において輪島市で発生した大規模火災では、焼失面積約4万9千㎡・約240棟焼損し、出火から14時間後に鎮圧された。具体的な発火源・着火物等の特定に至っていないが、地震の影響により電気に起因した火災が発生した可能性は考えられる。
こうした中、総務省消防庁は、「感震ブレーカーの普及推進に向けた会議」を実施。大規模地震時の電気火災対策として、感震ブレーカー等の普及推進に向けて取り組みの進め方などを議論している。
一部の都道府県・市区町村では、感震ブレーカーの設置・購入費用に対する支援を実施。令和6年度の消防庁・内閣府調査によると、10府県(47都道府県実施率約21・3%)・200市区町村(1741市区町村実施率約11・5%)が支援を行っている。
同庁では、内閣府・経済産業省と連携して感震ブレーカーの設置を進めてきたが、令和4年9月時点で感震ブレーカーの設置率は5・2%(参考値)に留まり、普及推進の加速化が求められている。また、感震ブレーカーの設置・購入費用に対する支援等、これまで積極的に進めている市区町村からは「感震ブレーカーの認知度が低い」、「電気火災を防止する効果が知られていない」、「各戸の状況に合わせて感震ブレーカーを設置しようとする場合、どの製品を選べばよいか分からない」、「感震ブレーカーを購入しようとする場合、取扱店が少ない」等といった声があがっている。
このような背景を受け、東京都では令和7年度の新規事業として、感震ブレーカーを設置する「分譲・建売住宅」等を新築する住宅事業者への補助を実施する。8月頃運営事務局を設置し、補助金申請受付など開始する予定だ。東京都は、今後感震ブレーカー設置の促進や消火器設置などの推進により、地震発生時の火災による人的・物的被害が約7割減少すると推計。2030年度までに都内における感震ブレーカーの設置率25%を目標に推進するとしている。
【日本住宅新聞2025年4月15日号より一部抜粋】
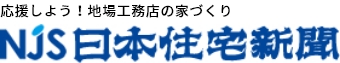


.jpg)

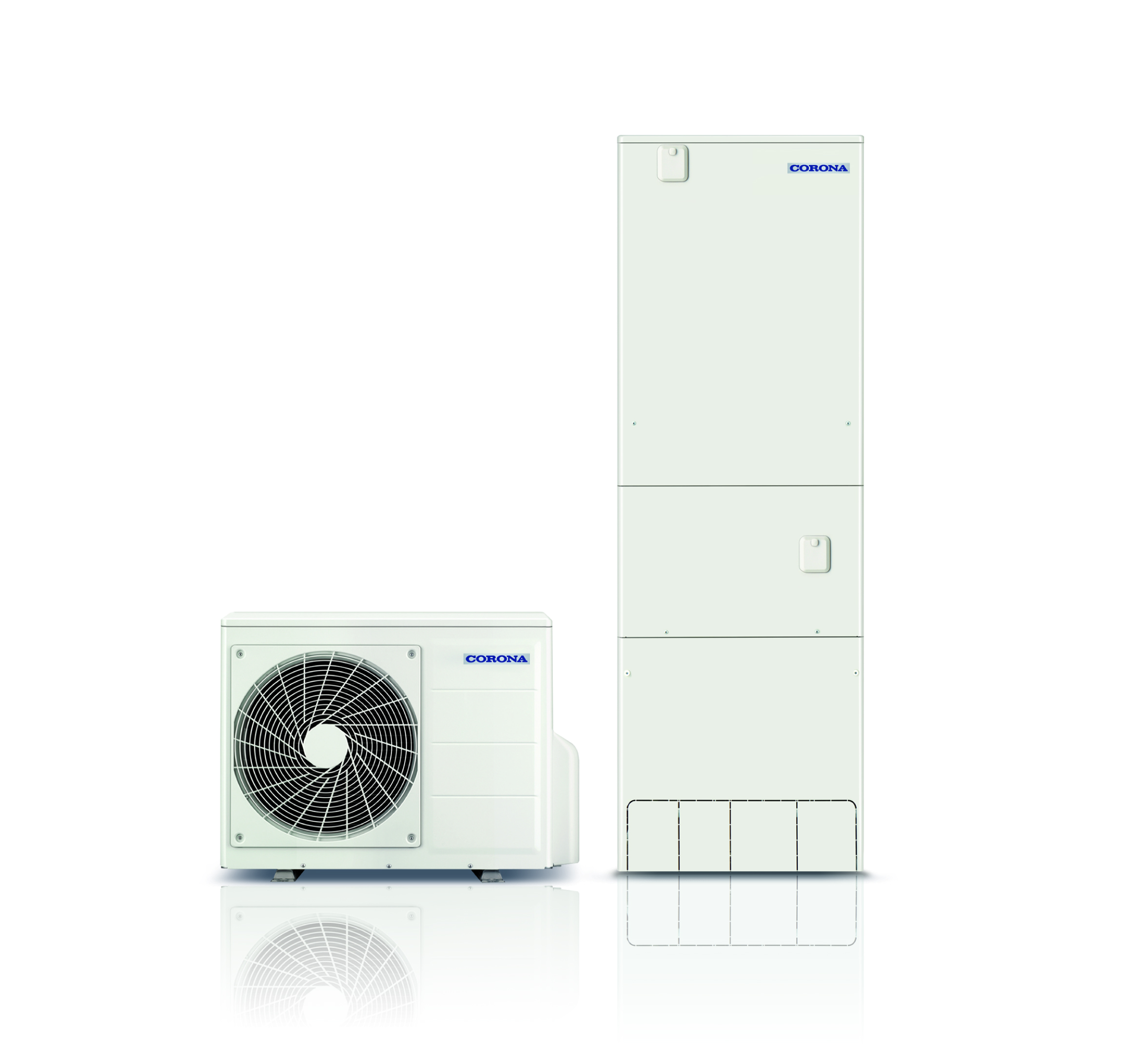
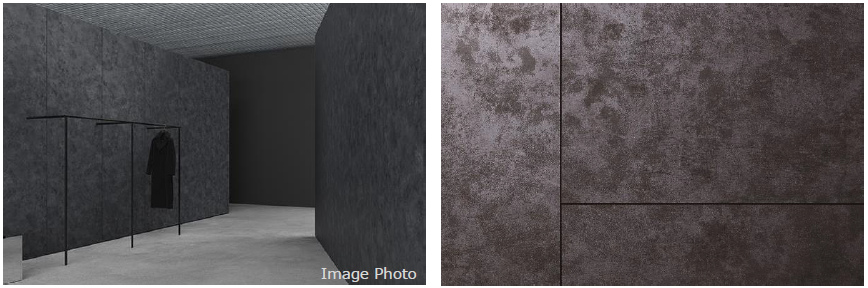



.png)