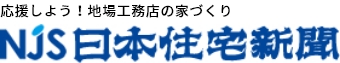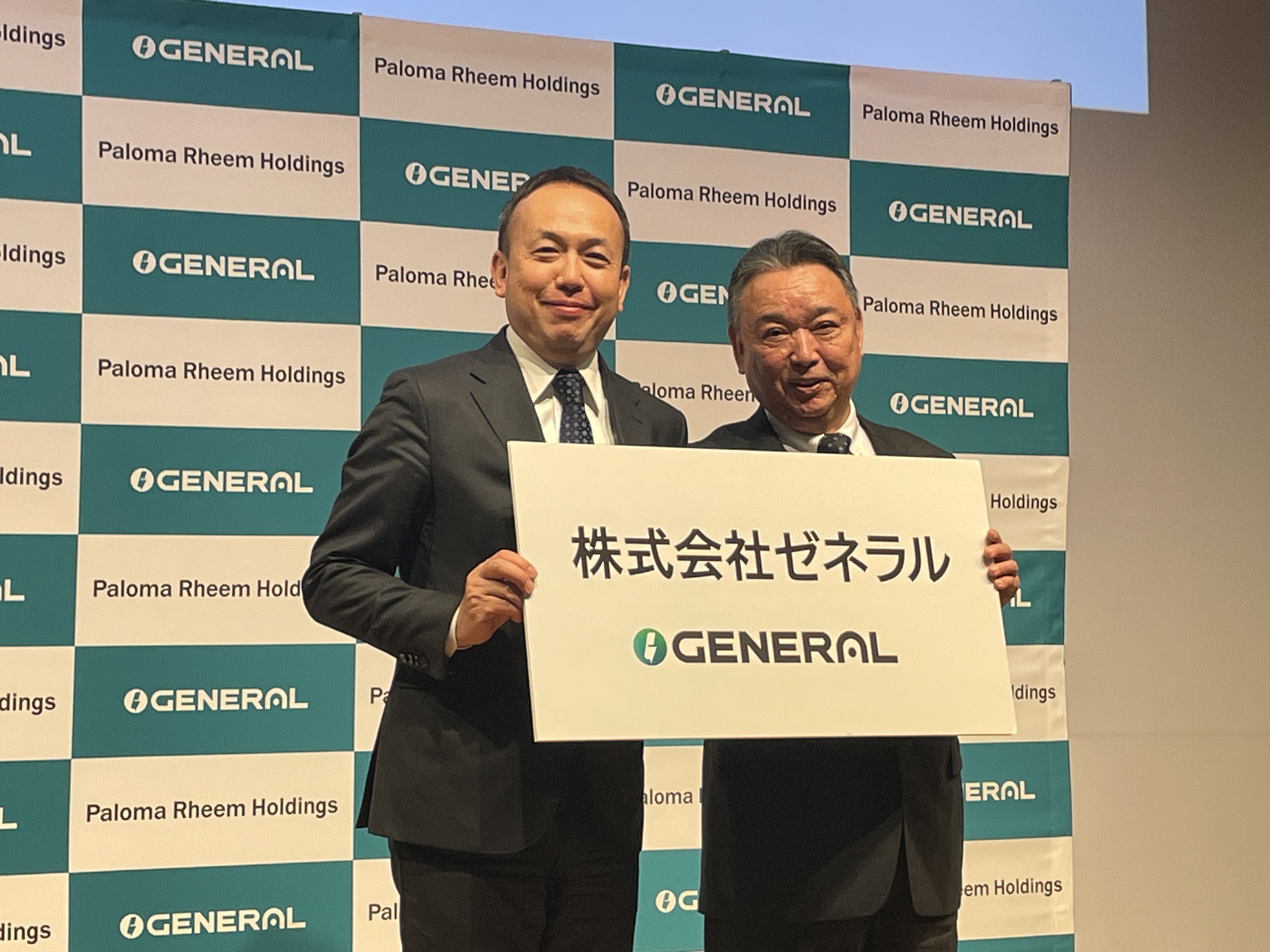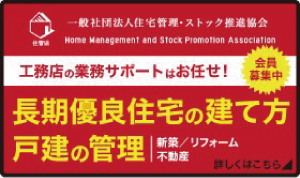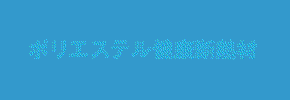改修5年後追跡調査、医学的知見を蓄積
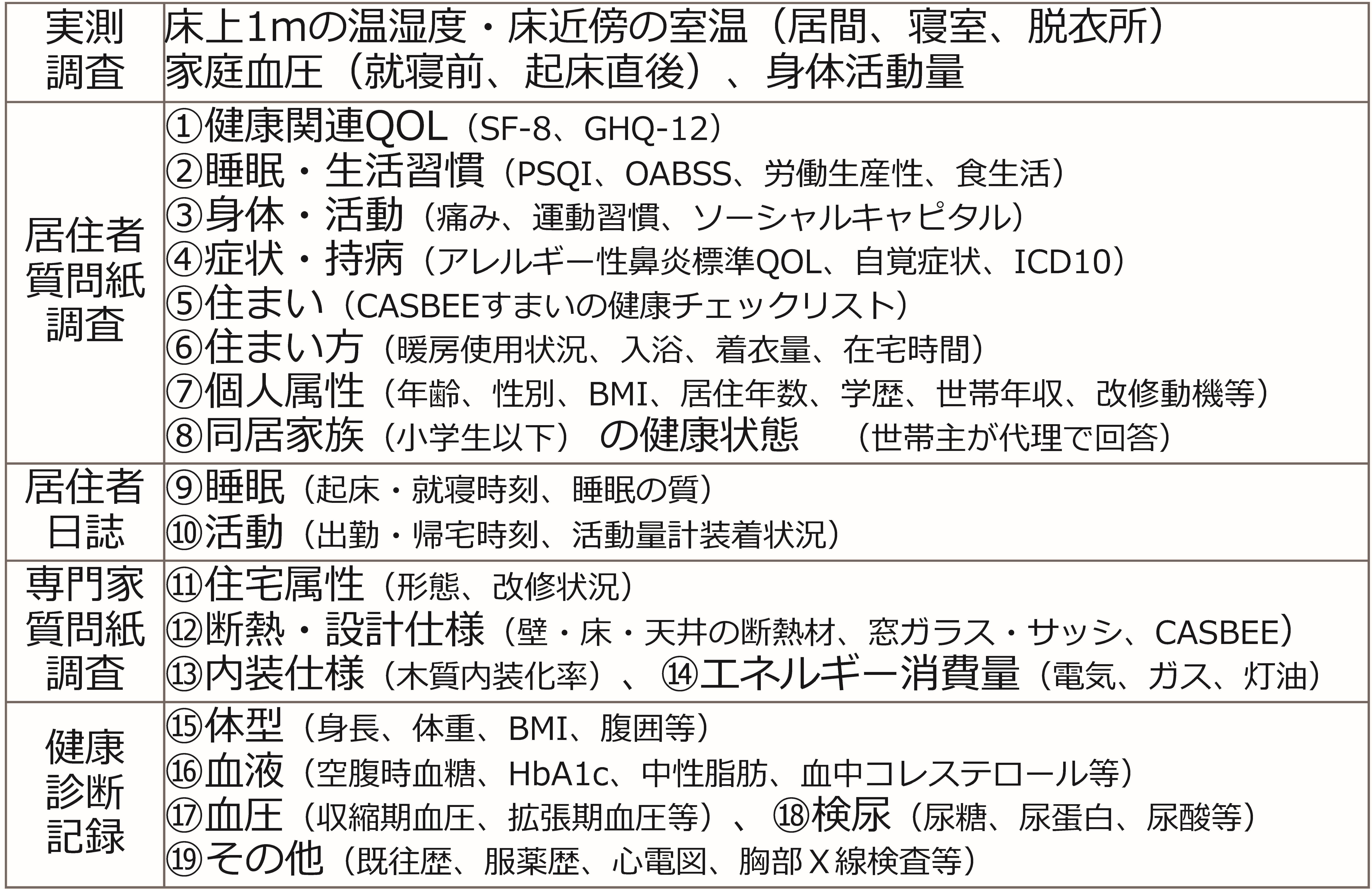
住宅の省エネ化を進めるため、断熱化により例えば光熱費が下がる、快適性が向上するといった住まい手が実感できるメリットを示していくということが課題だ。そして、最近では特に住まい手の健康を考えることが重要となっている。
こうした中、(一社)日本サステナブル建築協会は、「住宅の断熱化と居住者の健康への影響に関する全国調査第9回報告会」を2月13日に開催。同報告会では、国土交通省スマートウェルネス住宅等推進事業調査に基づく、住宅断熱の医療経済評価などの最新医学論文成果と、改修5年後追跡調査速報などを発表した。
これまでの全国調査では、同事業(2014~2019年度実施)で改修工事費補助を受ける世帯に調査を依頼し、改修前後の住環境と健康データを収集。比較対象として、改修しない世帯のデータも収集した。
さらに、長期的な追跡調査として、2019年度からは長期コホート調査(2023年度末に調査完了)で、質問紙調査と室温測定などを開始。2020年度からは改修5年後調査(2024年度末に調査完了見込み)で、上記の調査項目を収集し、断熱と健康に関する更なる知見の蓄積を目指した。
そして、これまでに医学論文14編、総説1編を刊行。室温においては、「WHOの冬季室温勧告18℃を満たさない住まいが9割。温暖地の住まいほど低温」などのエビデンスを発表した。家庭血圧では「断熱改修によって最高血圧が平均3・1㎜有意に低下。ハイリスク者ほど効果大」など、健康診断数値では「室温18℃未満で、心電図異常所見が有意に多い」など、疾病・症状では「就寝前居間室温が12℃未満の住まいでは過活動膀胱が1・4倍有意に多い」など、身体活動量では「床近傍室温が18℃以上の住まいでは住宅内転倒が12℃未満の住まいの1/2」などを発表。
さらに、医療経済評価では「断熱性能が高く暖かい住宅で暮らすことで、健康寿命が延伸し、費用対効果が高い」、総説では「高血圧・循環器疾患は『生活環境病』でもある」と新たな指標となる知見も提示した。
そこで、厚生労働省ではこれらの成果も参照し、2023年5月に厚生労働大臣が告示した「健康日本21(第三次)」において、「建築・住宅等の分野における取組と積極的に連携することが必要」とはじめて明記した。さらに、2024年1月には厚生労働省「健康づくりネット」の新設ページ「室温と高血圧、睡眠との関係」に、これらの医学論文成果と居間・寝室・脱衣所・トイレの室温チェックシートを紹介している。
(一財)住宅・建築SDGs推進センターの伊香賀俊治理事長(慶應義塾大学名誉教授)は、「この10年、現時点で73人、発足当時90人、北海道から鹿児島県まで全国の医学系、建築系のメンバーで取り組んできた。さらに、その細かな分析については研究室の当時の学生の貢献によるところも大きかったと思う」と発言。関係者に感謝の言葉を述べた。
また、改修5年後追跡調査で終わるのではなく、10年後追跡調査も行うことでより強固なエビデンスが得られると取り組み継続の期待の声もあった。断熱改修は住まい手の健康に寄与するもの。更なる研究の発展が期待される。
【日本住宅新聞2025年3月5日号より一部抜粋】